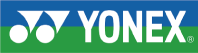渡邊哲さんの他にもう1人、テニスの試合の際に僕を泊めてくれる仲間がいました。
横浜に暮らす、脇三郎君です。
東京方面で試合があるときは渡邊先輩のアパート、神奈川方面のときは脇君の家と、ゲームの開催地に応じてそれぞれのご自宅にお世話になっていました。
脇君は僕と同学年で、全国3位というトッププレイヤー。彼と初めて出会ったのはまだ小学生の頃でしたが、すぐに二人はすぐに親友になりました。彼のご両親も、僕にとても親切にしてくださり、夏休みともなると、何度となく長期間にわたってご自宅に泊まらさせてもらっていました。
中学生になっても、夏休みの間中ずっと、僕らはいつも一緒でした。昼間は共に練習や試合をして、その後は夜の街へと繰り出しました。お兄さんのいる脇君は僕よりも少し大人っぽく、彼と過ごす横浜の夜はとても刺激的なものでした。音楽をやっていたお兄さんの影響でギターを習うようになった彼は、演奏がとても上手く、よく街中で弾き語りをしていました。夜遅くなっても人通りの絶えない道端で、傍らに座って彼が奏でるメロディを聴いていると、宇都宮とはまるで別の時間が流れているように思えました。
スポーツマンで頭も良い脇君は、学校でもモテたようで、ときどきクラスメイトの女の子たちを呼ぶこともありました。彼女たちもどことなく大人びていて、僕の中学校の女子たちとは異なる雰囲気を漂わせていました。中には芸能プロダクションに所属しているほどかわいい子もいましたから、僕にとって中学時代の夏休みは、とても甘く華やかな日々でした。僕らは特に何をするわけでもなく、夜の公園でただおしゃべりをして過ごすだけなのですが、それがとても楽しい時間だったことを強く憶えています。
宇都宮にいる時は、家では父に怒鳴られ、学校では孤独感に苛まれていたのに、横浜ではまったく別の、穏やかな世界に身を置くことができたのです。ささくれ立った僕の心も、やさしい空気に包まれてゆっくりと癒されていきました。荒涼と平穏、二つの世界を行ったり来たりする僕は、絶えず軸足が定まらず、常に情緒不安定な少年だったのです。
中学3年生も後半となると、そろそろ進路について真剣に考えなくてはなりません。6年生の時に行ったアメリカ遠征がどうしても忘れられない僕は、高校には行かず働いてお金を貯め、自分の力でもう一度アメリカに行きたいと考えるようになりました。家が貧乏だったからというよりも、父に援助してもらうのが嫌だった、というのが本音です。もしまた父にお金を出してもらったら、今まで以上に恩着せがまし態度をとられることは目に見えています。義務教育を終えたらもう父の世話になりたくない。自分の力で生きていきたい、僕はそう感じていたのです。
僕がこの計画を密かに温めていた頃、そうとは知らない担任の先生は、僕に進学の話を持ってきてくれました。宇都宮市内の私立高校が、テニス部に入ることを条件に、僕を推薦枠で受け入れてくれるというのです。学校をサボってばかりだった僕はただでさえ出席日数が少なく、高校に入学することすら難しいと思っていた中での朗報です。心の中では働くことを決意していた僕ですが、こんな自分に声を掛けてくれる学校があることがうれしくて、とりあえず話を聞いてみることにしました。
早速、担任が先方の高校に連絡を入れ、数日後にテニス部顧問の先生が僕の自宅まで足を運んでくれました。その方が、宇都宮学園高校(現・文星芸術大学附属高校)の上野一典先生でした。先生はまだ15歳の僕に対し、きちんと真正面から丁寧に自分の気持ちを話してくださいました。
「まだ設立間もない宇都宮学園のテニス部は結果が出せずに低迷している。何とか強化していきたいので、そのためにぜひ君の力を貸して欲しい」。それが上野先生からの話でした。
そんな先生の真摯な姿勢に感銘を受け、普段はひねくれている僕もまた、正直に自分の気持ちを伝えることができました。
「僕の力を評価してくれるのは本当に感謝しているが、僕はこれ以上父の世話にはなりたくない。テニスは好きだし続けたいが、今の僕にとっては父から自立することが最優先だ。もし進学すればあと3年は父の世話にならなくてはなない」。そう打ち明けたのです。
僕の話を聞いた先生はしばらく黙り込み、そしてこう切り出しました。「最初からは無理だが、もし君が宇都宮学園のテニス部に入り、我が校の選手としてインターハイに出場できたら、それ以降は学費免除にさせてもらいたい」と言ってくれたのです。
これには僕は驚きました。だってその瞬間まで、学費を理由に進学を断ろうと思っていたのですから。
先生の提案を聞いた僕は、自分の気持ちがよくわからなくなってしまい、その場で返事はできなませんでした。「ゆっくり考えてお返事しますので、もう少し時間をください」。そうお願いして、その日は面談を終えました。
僕の心は大きく揺れ動きました。自分ですら肯定できないこの僕を必要としてくれていること。僕の願いにも誠実に向き合ってくれていること。何よりそれが嬉しかった。一度は諦めかけた進学への意欲が、むくむくと沸き上がってくるのを感じました。その後、県外も含め複数の高校からも推薦入学のオファーをいただいたのですが、一番最初に声をかけてくれた宇都宮学園に進学することを、僕は決意します。なによりも上野先生の期待と情熱に応えたかったのです。
とまあ、ここまでは良い話なのですが、これには後日談があります。実は最初から、父が担任教師に掛け合い、どこかテニス特待生として僕を受け入れてくれる高校がないか頼んでいたらしいのです。あの父が、です。
それを受けて担任の先生が見付けてくれたのが宇都宮学園だった、というのがこの話の真相なのです。
僕がこの真実を知ったのは大人になってからだったのは幸いでした。なぜなら、もしこの段階で知っていたら、きっと激しく反発していたに違いありませんから。場合によってはひねくれて、転落の人生を送っていたかもしれません。今では笑い話ですが、ホントしゃれになりません。