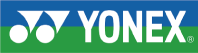佐藤政大ヒストリーズ
父・政雄、母・久子と出会う

1972年10月15日。僕・佐藤政大は、母の実家がある東京都立川市で生まれました。
栃木県宇都宮市で医療機器販売会社のエンジニアとして働く父・政雄と、父を献身的に支える母・久子との間に命を授かったのです。僕は、どこにでもいるような、ごく普通の幸せな家庭の子として誕生しました。そしてこの頃、宇都宮の自宅で僕たちの帰りを待つ父にある出会いがありました。そう、テニスとの出会いです。そして父とテニスのこの出会いが、やがて僕たち家族の将来に大きな波乱を巻き起こすことになるなど、この時はまだ誰も知る由もありませんでした。
父・政雄は、1946(昭和21)年に福島県の中央部に位置する郡山市で生まれました。しかし父が小学校1年生の時に両親が離婚。幼い父はまだ就学前の弟とともに、父親、つまり僕の祖父に引き取られ、祖父の勤め先のあった海沿いの町、小名浜町(現在のいわき市)で暮らすことになりました。親子の生活は、決して楽なものではありませんでした。母がいなくなったため、小さいうちから自分のことは自分でやらざるを得なず、炊事や洗濯などの家事一切を兄弟2人で行っていたそうです。
父は弟の面倒を見ながら、新聞や牛乳の配達、納豆売りなどで家計を支えつつ、地元の工業高校へ進学。電気科で回路の理論などを学んだ後、18歳で東京・三鷹にある医療機器メーカー・I社に就職しました。大手通信機器メーカーの子会社であるI社は、今では数千名が働く大企業ですが、父が就職した1964(昭和39)年頃は、まだ従業員30名ほどの小さな会社でした。父はこのI社で試作機を組み上げる技術者として採用されましたが、他の社員の多くは医系・理系の大学を卒業した研究者でした。実務である機械製作は得意分野だったこともあり、高卒の父でもさしたる問題はありませんでしたが、医学用語として使用されるドイツ語や、開発の現場で使われる英語の学習に苦労させられたと言います。
この当時、I社が世界で初めて製品化したのが「超音波診断装置」という検査機器です。今ではどこの医療機関でも当たり前に行われている、エコー検査機ですが、この時代に於いてはとても画期的な新製品だったようで、発表されるや否や、この装置は医学会の注目を集めたといいます。それにより会社の業績は急拡大し、I社は一躍世界の最先端企業の仲間入りを果たしたのです。
時代は高度経済成期。世の中全体が右肩上がりの豊かさを謳歌していました。そんな折、I社では会社主催によるダンスパーティーが開かれることになったそうです。世間からは花形企業のサラリーマンとして持て囃されてはいましたが、田舎の貧しい家庭に育った父にとって、「ダンス」はまるで雲の上の世界の文化であり、ステップひとつ知らないのが実情でした。父はどうしたら良いかわからず困り果て、とりあえずダンスレッスンに通ったのですが、生まれて初めてのダンスはどうにもハードルが高いものでした。何回通っても上達の糸口すらつかめず、パートナーをつとめてくれる女性にも迷惑をかけてばかりでした。練習を重ねる度に自分が情けなくなり、隅のベンチでしょんぼりと座り込んでは、いつも途方に暮れていたそうです。そんなある日、いつものように父がベンチで凹んでいた時のことです。ふと横を見ると、同じようにしょんぼりと沈み込んでいる女性の姿が目に入りました。その人は大手都市銀行の国立支店に勤務する、奥ゆかしくて可愛らしい女性だったそうです。互いの似通った状況を自然に察した二人は、どちらともなく練習ペアを組もうと言うことになり、気が付けばすっかり意気投合してしまいました。そう、これが、父・政雄と母・小林久子の運命の出会いとなった瞬間です。とはいえ実はこの時、母には結婚を夢見る相手がいたらしいのですが…。
幼い頃に母と別れ、当時も会社の寮で一人暮らしをしていた父は、家庭的な手料理の味に憧れていたそうです。いいえ、飢えていたと言った方が正確かもしれません。そのことを知った母は、両親と妹の4人で暮らす立川の自宅に父を招きました。若さ故か、年がら年中ただでさえ腹をすかしていた父は、それは美味しそうに小林家で出された食事を平らげたそうです。その食べっぷりにすっかり気を良くした母の母、つまり後の僕の祖母は、それからも父を頻繁に自宅に招いては、自慢の手料理を振る舞ったそうです。
母には弟がいましたが、数年前に家を出てしまっており、当時の小林家は両親と娘2人の4人家族。そのようなこともあって、父はまるで小林家の息子のような存在となりました。しかも、愛情込めた手料理を作るそばから皿まで食べてしまいそうな勢いで完食してしまうほどですから、祖母は父をたいそう気に入ってくれたそうです。いつしか父は、小林家の家族の一員のようになっていったのでした。そんなある日、祖母は父にこう切り出します。「寮を出て、この家に下宿したらいいじゃない?」と。聞けば妹さんが就職のため家を出ることになり、部屋が1つ空くとのこと。善くも悪くも真正直な父は、遠慮することを知りません。ひと様からの好意はどんなことであれ有り難く受け取る性格ですから、この時も二つ返事で「じゃあ、お願いします!」と嬉しそうに答えたそうです。何より、おいしい食事が毎日食べられるのです。まさに願ったり叶ったり。こんなチャンスを父が見逃すはずはありません。
母の結婚相手として、最初に父を意識したのは祖母でした。その真っ直ぐで大らかな人間性に加え、勤務先の安定性も申し分ありません。この人なら、安心して娘を嫁がせられると思ったのです。一方で母はといえば、想いを寄せていた人がいたものの、ちょうどこの頃は互いの心の距離が離れてしまっていたそうです。それに、同じ屋根の下で暮らす父ならば、この先一緒になっても気兼ねせずにいられると感じたのでしょう。すでに情も移っていたこともあり、この結婚話はトントン拍子に進んでいったそうです。
そして迎えた1970(昭和45)年、二人は正式に入籍しました。父24歳、母23歳でした。当初は国立市内に小さな家を借り、穏やかな新婚生活を送っていたのですが、転機はすぐに訪れました。2年後に栃木県で新設される自治医科大学に、I社の超音波診断装置が納入されることになったためです。当時はまだエコー検査の黎明期であり、医療機関に超音波診断装置を設置しても、現場では誰ひとりとして使いこなせる人材がいませんでした。それだけでなく、装置を使った診断技術を確立し、臨床応用の道を切り開くなど、医療従事者にとってもさまざまな課題が広がっていたのです。そこで父は、I社のインストラクター兼エンジニアとして開設準備中の自治医科大学に赴任し、現場のドクターたちとともに、超音波診断の実用化の方法を探るよう命じられたのです。
(テキストは著作権により保護されています。(C)佐藤政大 小貫和洋)