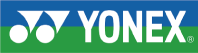幼い頃はテニスの練習をする父に連れられて、コートでボールやラケットを使って遊んでいた僕ですが、実際に競技としてのテニスを習い始めたのは小学校に入学した頃でした。その後、小学校3年生となると、父がテニススクールを開校したことを契機に、ジュニアクラス生の一員として本格的にレッスンを受けることになりました。父の指導法は、ただひたすら「ボールをコートの中に打ち返す」ことの一点張り。なんでも、父が全くの初心者だった時、憧れの生井さんから教わった指導法なのだそうです。
初めは何の疑問も感じることもなく、ただ素直に父の言うことを守って一生懸命練習していたのですが、1年も過ぎると単調な指導法と厳し過ぎる父の姿勢にだんだん嫌気が差してきます。学校が終わったら、すぐに父が待つスクールに直行しなくてはいけないのですが、それが嫌でいつも近所の駄菓子屋に寄り道をしてから帰っていました。お目当ては当時大ブームを巻き起こしていた「インベーダーゲーム」。僕もご多分に漏れずハマっており、このゲーム機が置いてある駄菓子店に行っては、友達と競うようにインベーダー相手に闘っていたのでした。
とはいえ、父が脱サラしてしまった我が家は経済的に厳しい状態。当然ながらお小遣いもごく僅かです。少ない金額でゲームを楽しむには、とにかく強くなるしかありません。負けない限り、ゲームオーバーにはならないのですから。そんな訳で、ゲーム上達に対する僕のモチベーションは、テニスに対するそれとは比べ物にならないほどグングンと盛り上がり、それに比例して腕前もドンドンと上がっていきました。
しかしながら、インベーダーたちは非常に強く、ゲームに勝つことは簡単ではありません。僅かなお小遣いはあっという間に底を突いてしまいます。そんな時、僕は夜中にそっと父の部屋に忍び込んでは、財布から小銭を失敬させてもらっていました。しかし当時の父は全く気がついていないようでした。大人になって、そのことを話したところ、父は特に気に留めることもなくただ笑うだけでしがた、しかしもし当時バレていたら、どんなに酷い罰が待っていたのか。想像するだけでゾッとします。
実は父には内緒なのですが、この件については後日談があります。ある日、担任の先生が母を学校に呼び出し、こう尋ねたそうです。「佐藤君はずいぶんとたくさんお金を持っているみたいだけど、どうしてなんでしょう?」と。先生は僕がどこかでお金を盗んでいたら問題だ、と母に注意を促したのです。学校から戻った母は、心配そうにそのことを問いかけました。そして僕は素直に「お父さんの財布からくすねた」と打ち明けました。優しい母には、どんなことでも正直に話せたのです。母は「先生は政大のことを心配していたんだよ。お母さんから先生にはきちんと伝えておくから、もうお父さんの財布からお金をとったりしちゃダメだよ。わかった?」と僕をたしなめました。母は僕を叱ることはあっても、感情的になって怒るようなことはしない人だったのです。
対する父はと言えば、僕がまだ幼い頃は優しかった記憶もあります。けれど僕が本格的にテニスを習うようになると、指導者としての厳しい側面が目立つようになりました。また、家計が厳しかったことも影響していたのでしょう。イライラすることも多くなり、僕は何かあるとすぐに怒り出す父のことがだんだんと嫌いになっていきました。
ある晩のことです。父がまた癇癪を起こし、母に辛く当たっていました。男として母を守りたいという激しい衝動に駆られましたが、小学生の僕では屈強な父にはまるで歯が立ちません。どうにもこうにもムシャクシャが治まらない僕は、父への抗議の意味を込めて幼い妹を連れて家出しました。といってもまだ子供ですから、家出の場所はすぐ近所。隣接する県立運動公園にラグビー場があり、グラウンドをが囲むように土手があったのですが、その土手の下、家からわずか徒歩1分の場所でした。どうしてそこに行ったのかは憶えていませんが、真っ暗な中で遠くに行くのは怖かったのかもしれません。あるいは小さな妹の体力を考慮して、遠出するのを避けたのかもしれません。
ですがとにかく、父に対して面と向かって反抗できたことに、「やってやったぜ!」という興奮を抱いていたのは確かでした。そんな想いの中、自宅からすぐそばの芝生の上に置かれたダンボール箱の中で、僕たちはじっと息を潜めていたのです。父が僕たちを捜しに来たのは、それから間もなくでした。父は僕たちを叱ることもなく、「帰るぞ」といって僕たちの手を引いて、3人で土手を登っていったのでした。そうして僕たちの家出は、あっけなく幕切れを迎えましたが、不思議なことにさっきまであんなに父に憤っていたにも関わらず、その時の僕は、なぜかほっとするような安堵の気持ちを感じていたのでした。
父がテニススクール開校してから1年ほどすると少しずつ生徒の数も増え、経営も徐々に軌道に乗り始めました。母はそれまで働いていた自動車工場を辞め、スクールで事務仕事を受け持つようになりました。その傍ら、母自らも父からテニスのレッスンを受け始めると、秘めていたその才能が瞬く間に開花していきました。国立で銀行員をしていた頃に、母にもテニス経験があったようですが、その時はほんのかじった程度。本格的にプレーするのはこの時が初めてだったそうです。しかし天性の才を授かっていたのでしょう。わずか1年ほどで、県の選抜大会で8位入賞するほどまでの腕前となったのです。僕の身体に流れるテニスの素質は、父だけでなく母のDNAを受け継いだものなのかもしれません。
しかしそのわずか1月後、1983(昭和58)年の3月、母は胃の調子が悪いと自治医科大学病院に診察を受けます。そして父が納めた超音波診断装置で相知のドクターに検査してもらったところ、うっすらとした陰影が胃の辺りに写っていたのです。しかしその時は大学病院に空き病床がなかったため、急遽ドクターの紹介で宇都宮市内の総合病院に検査入院することになりました。その時、母は何かを感じ取っていたのでしょうか、父に何度も「政大とクミコのことを頼みます」と語っていたそうです。ある日のこと、母はまたいつものように、父に我が子を想う気持ちを託したそうです。父は「わかったよ。二人のことは僕にまかせて。安心して治療に専念するんだよ」。そう言って母を落ち着かせ、家に帰って来ました。その話を聞いた僕と妹は、母の身を案じて詰め寄ると、父は「大丈夫だよ。検査で入院してるだけだから、すぐに良くなって帰ってくるよ」と言いました。その言葉は、今まで親戚や母の友人たちからも何度も聞かされていた話と同じでした。「本当に?本当に大丈夫なの?」。しかしその時です。重苦しい空気を突き破るように、電話のベルが家の中に鳴り響きました。なんだか嫌な予感がします。電話を受けた父の表情がみるみる曇って行きました。それは母が亡くなったという知らせだったのです。その話を父から聞いて、目の前が真っ暗になったことを、今でもはっきりと覚えています。母の死が本当だと理解しつつも、あまりに突然すぎてその現実を受け止められず、空虚な悲しみで心がいっぱいになりました。僕は大人たちを恨みました。「すぐにお母さんは良くなって帰ってくるよ」って言ったのに、と。
後に母の体を病理解剖をしたところ、直接の原因は検査のために飲んだバリウムが固まってしまったことだったそうです。しかし母の体を蝕んでいたのは、それだけではありませんでした。母の胃は、スキルがんという悪性の腫瘍に冒されていたことが判明したのです。スキルがんは通常の胃がんとは異なり、胃の表面の粘膜には発症せず、密かに筋肉の内側奥深くに病巣が広がっていきます。ですから、超音波やX線などによる検査などでも見つけ難く、母の場合もかなり進行してしまっていたそうです。遺伝や慢性胃炎、ピロリ菌なども原因となるのだそうですが、やはり一番思い当たるのは強いストレスです。激しい心労にさらされながら、苦しい家計を一心に引き受け、家族のために健気に振る舞ってきた母。その心情は如何ばかりだったのでしょうか。
母方の祖父は「娘はお前に殺されたんだ」と父をなじりました。そして僕もつい最近まで、それが真実だと信じてました。父のせいで母は死んでしまったのだと。その時からずっと、いつだって僕の心は荒んだままでした。けれど僕が大人になってから、ある一言で僕は救われました。母の友人が語ってくれたその言葉によって、何年も心に伸し掛かっていた、重くて窮屈な十字架から解放されたのです。そして優しく温かな感情に包まれました。それは、「あなたのお母さんは、本当に幸せそうだったのよ」という言葉でした。「大好きなテニスに打ち込む父の姿を見ることができて、それを支えることができた。そしてかわいい二人の子供たちに恵まれ、愛情に溢れた毎日を過ごせた。家族の幸せ。それこそが、彼女にとっての本当に幸せだったんだよ」と。
ありがとう、お母さん。僕たちはあなたの子供として生まれて、本当に幸せでした。
(テキストは著作権により保護されています。(C)佐藤政大 小貫和洋)