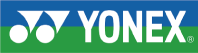テニスシューズの一件から間もなく、もうひとつの事件が起こりました。
僕の家は学校から3キロほどと距離があり、中学へは自転車通学をしていました。自転車通学する友達の多くは、中学校進学に合わせて変速機付きのスポーツサイクルを買ってもらうのですが、貧乏な我が家では新しい自転車を買う余裕などありませんから、僕は仕方なく小学生時代にかったボロボロの自転車で通学していました。
そんな中、不幸の女神が僕に微笑みます。東武カップというテニス大会に出場し、優勝を勝ち取ったのです。なぜそれが不幸かというと、その時に優勝賞品として渡されたのが、新品の黄色い自転車だったのです。といっても高価なスポーツサイクルではなく、ごく普通のシティサイクル、いわゆる「ママチャリ」でした。それでも僕にとっては、これ以上ないプレゼントです。
「やった!これで俺も新品の自転車に乗れる!」と喜びたかったのですが、ふと嫌な予感を感じました。「これに乗って学校に行ったら、またヤンキーの先輩たちに目を付けられる」。そう思ったのです。というのもママチャリに乗って良いのは、女子生徒とヤンキーだけ、というのが中学のローカルルールだったからです。
自転車をもらえたので、父は当然「これで学校に通いなさい」と言います。けれど僕は、いろいろと理由をつけて遠回しに拒否しようとしました。理由はもちろん、ローカルルールです。
するとそれが父の怒りに火を注ぎ、「そんなに嫌なら歩いて学校へいけ!」と怒鳴られる始末です。本当は「こんな自転車に乗っていたら先輩たちに殴られる」と言えば良いのでしょうが、やはり当時の僕にはそのひと言だけは、口が避けても言えませんでした。“甘え”かもしれませんが、言葉に出さずとも父が理解してくれることを望んでいたのです。しかし実際の父は、そんな僕の気持ちを察して寄り添ってくれることは決してありませんでした。学校でも家庭でも居場所を失った僕は、それから徐々に孤独を感じるようになっていったのです。
僕が孤独感を深めた理由は、他にもありました。僕以外の1年生には、“リーゼントにドカン”を決めた、僕よりもずっと悪そうな奴らもいたのですが、どういうわけか彼らは上級生からノーチェックです。
「どうして僕ばかり理不尽な扱いを受けなくちゃならないんだ」と、さらに心は擦り切れます。そしてある時気付いたのです。そういった輩には兄や姉がいて、それで大目に見られている、という事実を。
「ああ、僕にも年上の兄妹がいればこんな目に合わずに済むのに……」。そう考えれば考えるほど悔しさが募り、心の傷はさらに深くなっていきました。
今思えば、東京や横浜の友人たちと付き合いがあって、都会での遊びにも慣れ親しんでいた僕は、どこか生意気で危うい雰囲気を漂わせていたのかもしれません。地元思考が強く保守的なヤンキー達は、そんな僕が鼻についたのでしょう。
東京近郊のテニス仲間たちはみな、僕を仲間として受け入れやさしく接してくれているのに対し、むしろ地元であるはずの中学で孤立してしまったのは、皮肉以外のなにものでもありません。
また、僕の中学校には軟式テニス部はありましたが、硬式テニス部がなかったので、僕は放課後そのまま帰宅し、毎日父のテニススクールで練習していました。部活に入らなかったため、2年生3年生の先輩たちとつながりも持てず、いつもアウェー感満載の状況でした。僕は学校に行くのがだんだんと嫌になっていきました。父には仮病を使って学校を休み、学校には「試合に行くから」と嘘を付いて欠席し、家に閉じこもる日々が増えていきます。