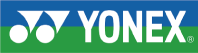今では考えられないことですが、僕が中学校に入学した1980年代は、個性的であることは許されない時代でした。
「皆と同じであること」が良いとされており、「個性を出すこと」=「非行の予兆」と見なして、教師から徹底的に指導を受けたのです。
入学当初の僕は、テニス以外は特に目立ったところもない、ごく普通の少年でした。しかし皮肉にもこの「テニス」が発端となり、ある騒動に巻き込まれていくことになったのです。
原因は「テニスシューズ」でした。校則の中で男子の靴は「白の運動靴」と規定されていましたが、学校の見解では「テニスシューズは運動靴ではない」とされたのです。「そんなバカな、テニスシューズだって運動靴じゃないか!」皆さんだって、そう思うでしょう?
当然ながら父もそのように主張したのですが、中学側はあくまで認めませんでした。恐らく「一人でも例外を認めると規律が崩壊するから厳格に対応すべき」ということなのでしょう。僕はどこからどう見たって非行少年にはなりそうもないのに、です。その時点で、すでに僕個人の性質や性格さえ、完全に無視されている状況です。
僕が学校にテニスシューズを履いて行かざるを得ないのは、家庭の経済事情も関係していました。財布に余裕がない中でも、父は「少しでも良い道具を使わせたい」との思いから、年に1回、1万円以上もするテニスシューズを買ってくれたのです。とはいえ年に1足だけですから、成長期を迎えた体に合わせ、いつもワンサイズ大きなシューズを購入し、毎年大切に履き続けていたのです。学校指定の運動靴は1足千円程度でしたが、その靴を余分に買うだけのゆとりは、我が家にはありませんでした。ですから僕は、父がなけなしの金を叩いて買ってくれた“ただ1足のテニスシューズ”を学校にも履いて行ったのです。
そんな僕に目をつけたのは、教師たちだけはありませんでした。中学を影で支配している「怖い先輩たち」もまた、テニスシューズを履いている僕が気に入らなかったようです。
初めは、廊下ですれ違い様にちょっかいを出される程度でした。しかしやがて、「これは何かおかしい」と感じるようなことが頻繁に起こるようになっていきます。
昼休みには、校庭では何組もの男子生徒たちが入り乱れてサッカーをしていたのですが、どういうわけか周りでプレーする先輩たちが、いつも激しく僕にぶつかってくるのです。当初は偶然かと思っていましたが、あまりにも頻発するので「ふざけているに違いない」と考えるようになりました。いいえ、それは「ふさけ」ではなく「いじめ」だったのです。本当はわかっていましたが、僕はそれを認めたくなかったのです。心のどこかでヤンキーたちのターゲットになっていることに気付きながらも、気が付かないふりをしていたのです。
認めてしまえば、自分が惨めになるから。それだけは、何としても避けたかったのです。
やはりテニスシューズが原因でした。ヤンキーたちは、キャンバス地のデッキシューズやバスケットシューズを好んで履いていましたが、その見た目が僕のテニスシューズと良く似ていたのです。そのような靴は、“不良として認められた者だけが履ける”靴だったのです。見た目が普通なのに、そういったシューズを履いている僕は、「1年のくせに生意気だ」と目を付けられたのです。
当時は147センチと小柄でしたから、僕よりも20cm以上も大きな3年生から受ける威圧感は相当なもので、まったくもって震え上がるような状況です。僕はただ、うすら笑いを浮かべてその場をやり過ごすだけで精一杯でした。
本当は、金銭的な問題から通学用とテニス用の靴を兼用していただけなのです。僕はたった1足しか靴を持っていなかっただけなのです。けれど僕には、そんな事情を説明する機会すら与えられませんでした。
学校にいる間は、いつも神経を張り詰めてばかりで気が休まりません。そればかりか、時には理由もなく殴られることさえあったのです。あの頃の時代、個性を出すことは「大人の世界」でも「子供の世界」でも、絶対にタブーだったのです。
僕は、普通の白い運動靴を履いて、それらの苦痛から解放されたかった。ですが父は、そんな事情はつゆ知らず、「テニスシューズだって運動靴なんだから、堂々と履いて行けばいい」の一点張りです。僕が何を言っても聞き入れてくれませんでした。それどころか言い返されること自体が気に入らないらしく、事情を説明しようとすると反抗的だと受け止め、余計に怒りに火がつく有り様でした。以前なら母が間に入って取り持ってくれたのですが、その母も今はもういないのです。
そんなある日、父は我慢の限界を超えたらしく「それなら俺が学校に行って話してきてやる!」と教師に直談判に出かけてしまったのです。僕にとっては最悪の状況でした。良くも悪くも情熱的な父の説得は功を奏し、交渉は見事に成功しました。僕は翌日から正式にテニスシューズを履いて行って良いことになったのです。
今になって思えば、父の「テニスシューズも運動靴だ」という主張を軸に行ったことは、全くもって正しい行動です。けれど、当時の僕としては受け入れがたいことでした。テニスシューズによる通学が、「大人のルール」でOKになったところで、「子供のルール」では依然として許されない行為だったからです。けれど僕には、父にそのことを伝えることができませんでした。「先輩に目の敵にされている」ことを認めたくなかったし、父に知られたくなかったのです。その背景にあったのは、僕の身勝手なプライドだったのかもしれませんし、あるいは父に心配させたくないという想いだったのかもしれません。ただ当時の僕には、そんな自分自身の複雑な心の奥底を見つめる余裕もなかったのです。
この当時の僕は、父と学校、先輩たちの板挟みとなって身動きが取れない状態でした。個性を発揮するには、素直でいることが何より大切ですが、この頃の僕は素直になれるどころか、心休まる時間すらありませんでした。そのことが長期間重なり、次第に僕の心はひねくれていったのです。
生まれて初めてタバコを吸ったのもこの頃のことです。「カッコいい」とか「好奇心」とか、そういった理由ではなく、ただ「ルールを破りたい」という気持ちからでした。大人たちに正論で言い返す力がないから、邪道で抗おうとしたのです。それは、「反抗」というよりも「抵抗」といった方が良いでしょう。それほど大きな力の差が、僕の前に立ちはだかっていたのです。
僕は1足しかないテニスシューズを大切に履き続けました。使い込むうちに、負荷のかかる親指の付け根の部分には穴が開いてしまいます。しかし新しいシューズを買うことができなかった僕は、穴の大きさに合わせてカットしたテニスボールを接着剤で貼付けて履き続けました。
2年生なって新しい靴を買ってもらっても、同じ部分に穴が開き、同じように修理しました。そして3年生なっても、また同じことを繰り返しました。父が血の滲む思いで働いて稼いだお金で買ってくれた、大切なテニスシューズなのですから。表面的には父に強く反発していた僕でしたが、内心では父に感謝していたのです。
……もしかすると、入学当初からこの継ぎ接ぎだらけのオンボロテニスシューズを履いていたならば、きっと上級生にからまれることもなったのかもしれません。