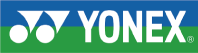僕が小学生だった昭和50年代当時、硬式テニスのジュニア選手は、ほとんどが富裕層の子息令嬢でした。テニスは今以上に「お金がかかるスポーツ」だったんです。
その頃はまだ、大人でさえも海外に行くことは人生の一大イベントという時代でしたが、ジュニア選手たちは小学生にもかかわらず、年に何度も海外遠征に出かけていました。硬式テニスとは、それが当たり前の世界だったんですね。
そんな仲間たちを見るにつけ、僕はただただ「いいなあ、みんな海外に行けて」と指をくわえて眺めていました。ですが、子どもながらも多額の費用がかかることはわかっていたので、「僕も海外遠征に行きたい」と口に出すことは決してありませんでした。それに、彼らをうらやましがるような態度も一切とりませんでした。そうしてしまうと自分が惨めになってしまうから、意地でも平静を装っていました。
その反面、心の中では「どうせ僕は海外に行けないんだ」と諦めきっていたのも事実です。周りのみんなは最新のテニスウエアで全身を固める中、普段着兼用のたった1着のジャージをいつも身につけていた僕は、コンプレックスの塊だったのです。
他方で僕は、全国小学生テニス大会に4年生の時から3年連続で栃木県代表として出場しており、そこそこの実力もありました。日本の各都道府県代表の選手が競い合う大会ですから、出場するのはほとんど6年生ばかり。その中でひとり、4年生で全国デビューしていた僕は、ジュニアテニスの世界ではそれなりに注目選手だったようです。
そんな僕を気にかけてくれたのが、ジュニアの育成に力を入れ、数多くの一流プレイヤーを輩出してきた名門テニスクラブ「桜田倶楽部 東京テニスカレッジ」の飯田藍先生です。僕たちは親しみを込め、「藍先生」と呼んでいました。
僕が6年生になった頃、桜田倶楽部が主催するアメリカ遠征ツアーがあったのですが、その機会に藍先生は「本気で息子さんの才能を伸ばしたいなら、可能な限り早い時期に海外経験をさせるべき」と父に声を掛けてくれたそうです。
本当の強豪テニス選手になるには海外経験が必須である、という事実は父も痛感していました。しかし当時はまだ、1ドルが250円ほどの為替レートだった時代。国内遠征と比べて、海外行きには桁違いに大きなお金が必要だったのです。決して暮らし向きが楽ではなかった佐藤家にとっては非常に莫大な出費となりますが、思い切りの良い父は最初で最後の大勝負と覚悟を決め、僕に切り出しました。「お前、アメリカ遠征に行ってみたいか?」と。後で聞いたのですが「せめて一生に一度くらいは海外遠征に行かせてやりたかった」とのことでした。もちろん僕は、そんな父の心の葛藤など知る由もなく、二つ返事で「行きたい!」と答えたのでした。どこからその膨大な費用を工面したのかは知りませんが、父が言うには「すっからかんの無一文になっちゃった」そうです。
最初に書いた通り、当時のテニスのコミュニティ内には「海外遠征に行くのが当たり前」とう雰囲気がありましたし、どの家庭もそれくらいの経済力があるのが普通でした。
そんな中、海外に行く仲間たちを、ひとり指をくわえて遠い視線で眺めていた僕は「やった!これで僕もやっとみんなの話についていける。」と感じたのです。誰にも悟られないよう抱え込んでいたコンプレックスから開放され、ついに僕にも報われる時が訪れた!と、浮き立つような気持ちで胸がいっぱいになりました。
ですから、清水の舞台から飛び降りる覚悟で費用を捻出してくれた父に、僕は素直に感謝をしていました。しかしその反面、父にはどこか「お前のために頑張ってやってやったんだぞ」とプレッシャーを発している面も感じられました。それまでも父は何かにつけ恩着せがましいところがあったのですが、今回の件でそんな父に対する反発心がさらに強くなったこともまた、紛れもない事実でした。
とはいえ生まれて初めての海外ですから、心は浮き立ちます。それどころか、飛行機に乗ることすら人生初体験です。そしていよいよ、出発の日を迎えました。忘れもしない1984年12月28日の朝、暮れも押し迫る中で僕は1人電車に乗り込み、集合場所である成田空港へと向かったのです。遠征に行くジュニア選手の多くは保護者同伴での参加でしたが、父は「妹の世話をする」と空港への付き添いさえしませんでした。あるいは、なけなしの全財産を使い果たした父は、見送りに来るお金すら無かったのかもしれません。それでも僕は、「アメリカに行ってテニスができる!」と大興奮でした。そして何よりも「みんなと同じように遠征に参加できる」ことが嬉しかったのです。もちろん、いつものジャージを着ての参加でしたが…笑。
一緒にアメリカに向かった参加者の中には、後にジュニアフェドカップ16歳以下日本代表監督となる、駒田政史選手の兄の姿もありました。今では日本テニス界のビッグネームとなった選手たちと幼いうちに親交を深められたことは、その後の僕の人生にとって大きな財産となりました。
搭乗した飛行機の中には、中学日本代表選手としてアメリカを転戦する先輩たちも一緒に乗り込んでいました。主催の桜田倶楽部が彼らのサポートも同時に行っていたのです。中学生も僕たち小学生も、ほぼ同じ日程で練習など行うため、現地に着いてから行動をともにすることが多々ありました。
先輩たちの中には、後年デビスカップで松岡修造氏とダブルスを組むことになる佐藤哲也さんや、トーナメントプレーヤーとして活躍される立見弘一さんの姿もあり、両先輩とも田舎から出てきた僕を、まるで本当の弟のようにかわいがってくれました。兄のいない僕にとって二人は、甘えることを許してくれた初めての年長者でした。彼らとの関係を通じて、僕は目上の人との付き合い方を覚えていきました。やさしく僕を受け入れてくれた二人の姿勢が僕に自信を与え、人を信頼して頼ることができるようになったのです。その体験は、その後も紆余曲折(うよきょくせつ)を余儀なくされる僕の人生において、大いに役立つことになりました。
苦境にあっても卑屈にならず、自分から心を開いて積極的に周囲にコミュニケーションをとる。そうすることで、必ずどん底から僕を救い上げてくれる人が現れます。今の僕があるのは、そうやって僕を支えてくれた多く方々との出会いによるところが少なくありません。その原点こそが、この時の体験だったのです。
今でもあの時の写真を見ると、期待と不安が同居したような、不思議な感覚が当時のままによみがえってきます。そこには、普段着兼用のジャージにペラペラのウインドブレーカーを羽織った僕が、こっちを向いて笑顔で問いかけているのです。
「お前、今でもチャレンジングスピリットを忘れていないか?」と。